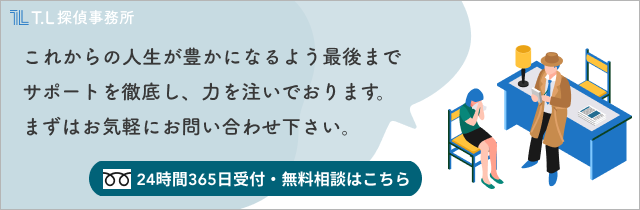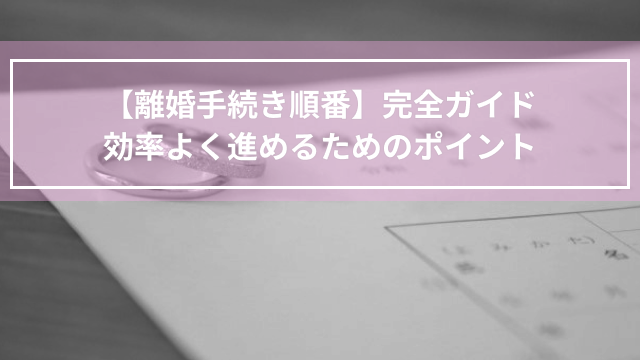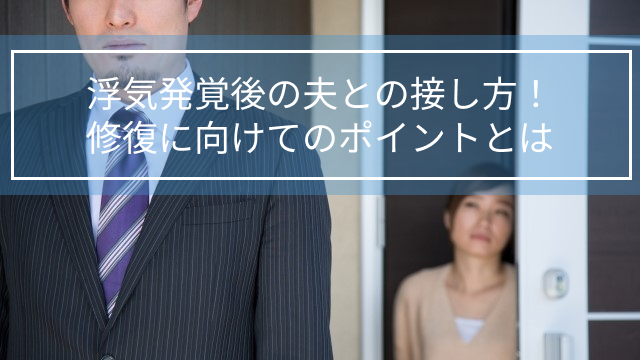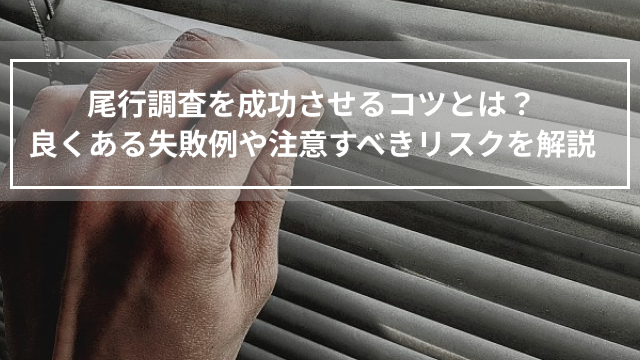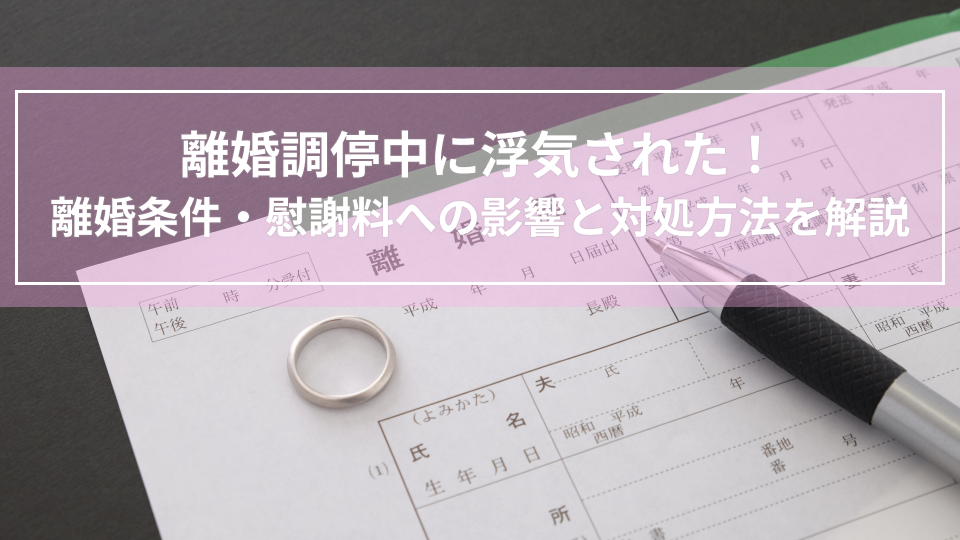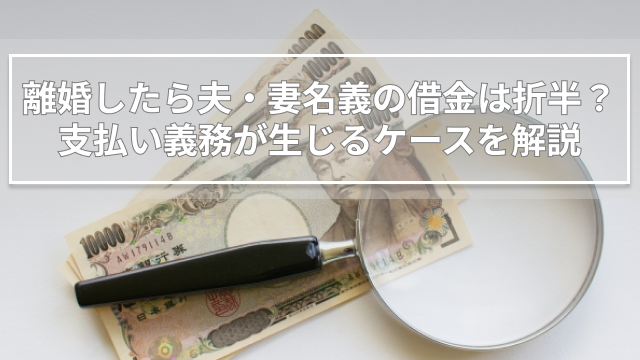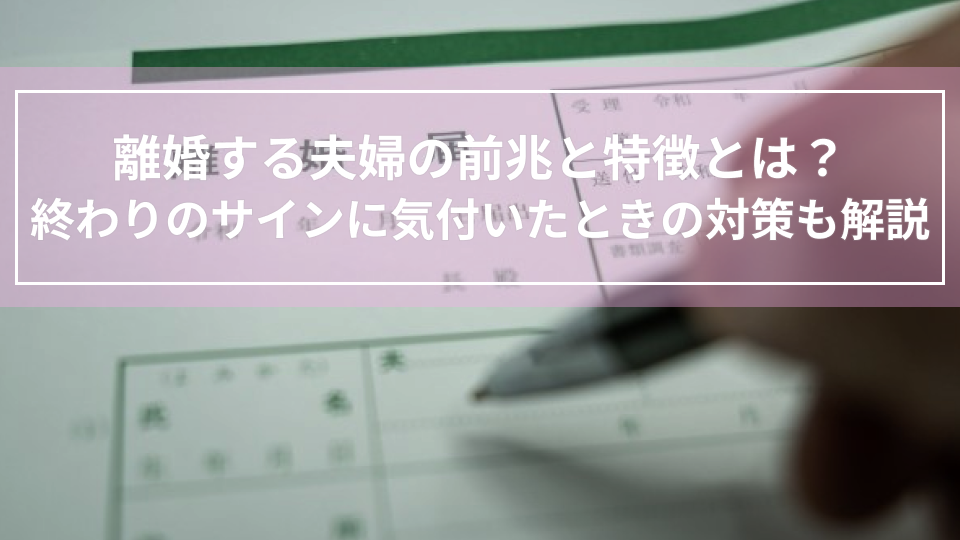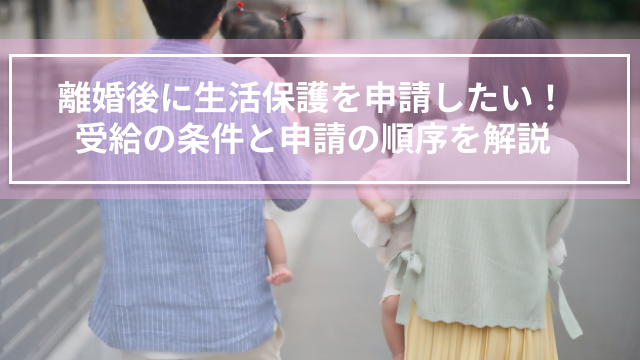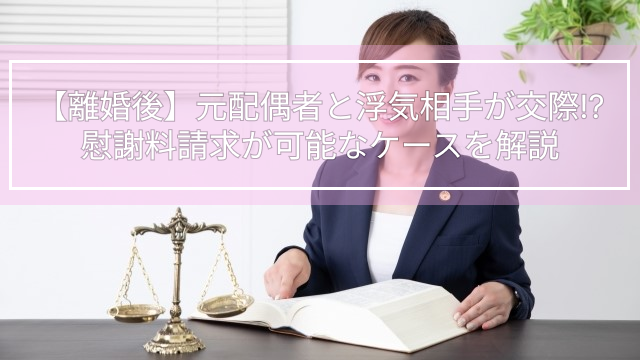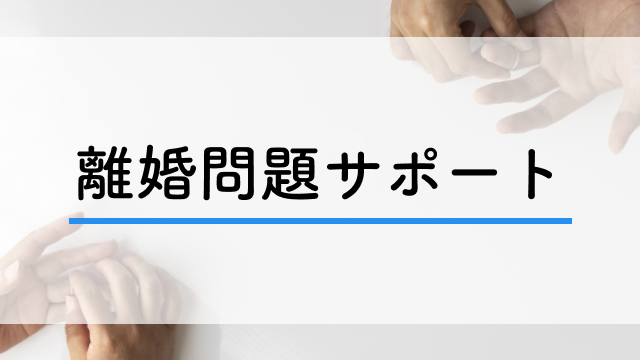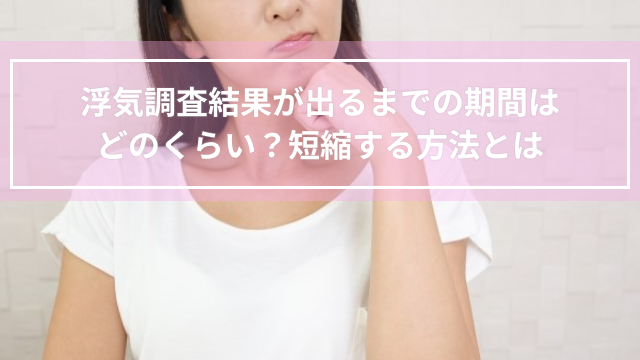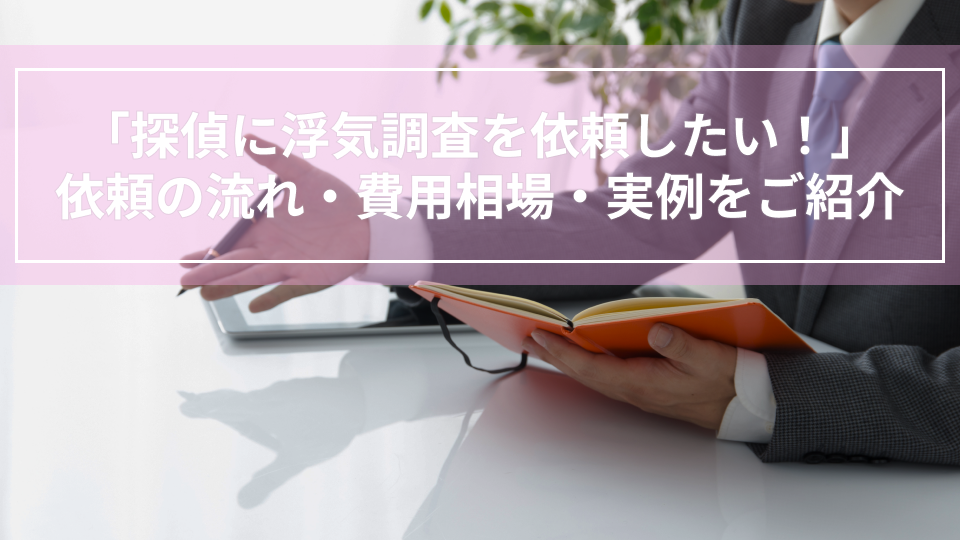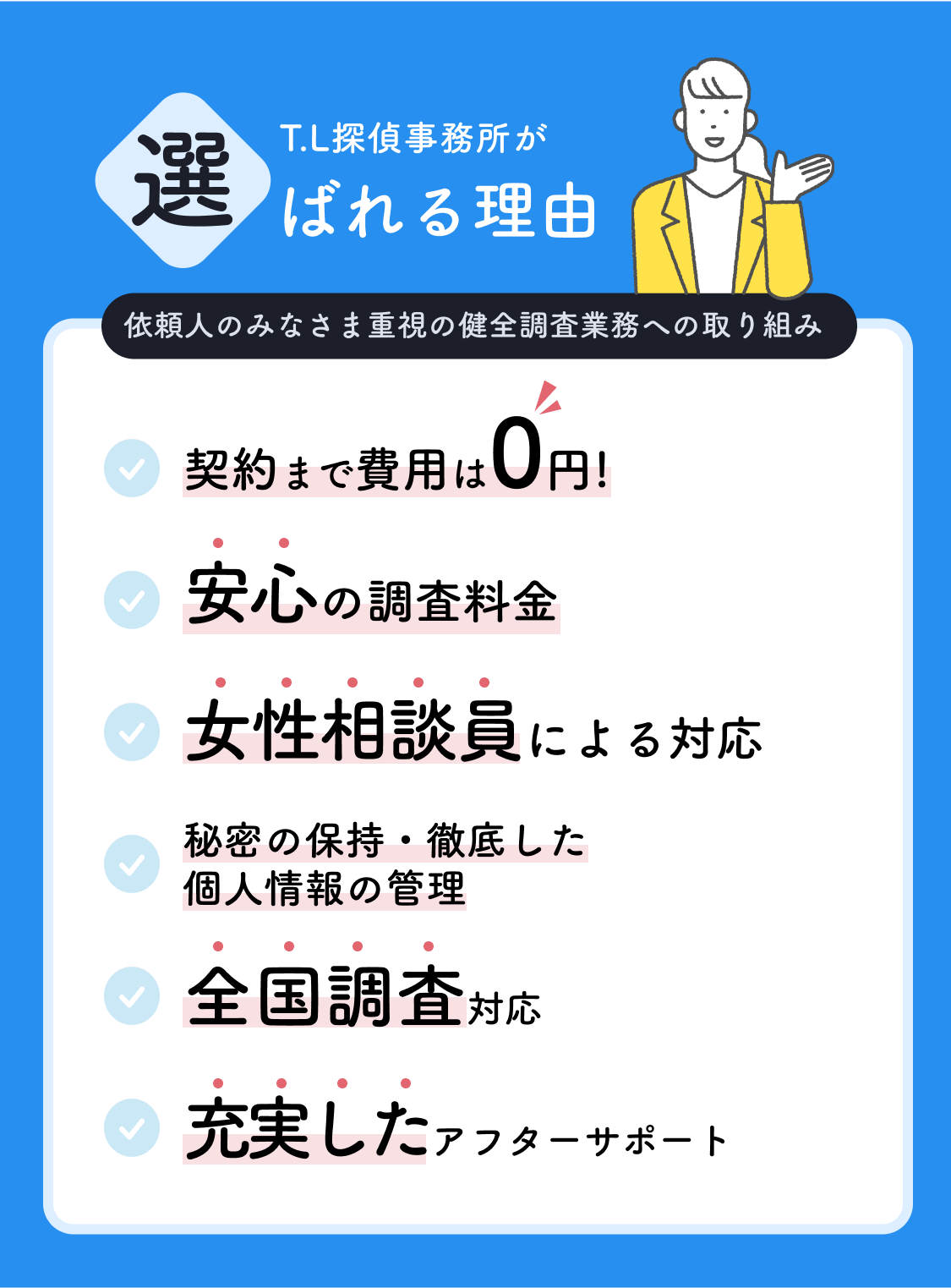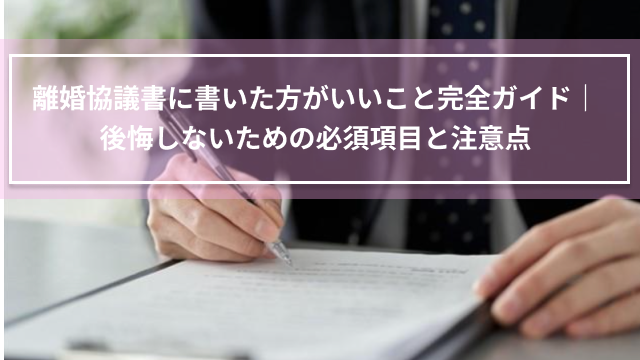離婚を決めてから切りだすまでにやっておくこと

離婚は人生を変える大きな出来事となります。
離婚を決めたなら、新しい生活に向けてしっかり準備していきたいですね。
そのためにも子どもやお金の事についてしっかり計画しておく必要があります。
まずは離婚後のライフプランを立てておきましょう。
毎月の生活費がどれくらいになるのか、どのような働き方ができるのか、どんな所に住むのかなど、新しい生活が始まった時、どんな問題が出てくるのかを考えてみるのが大切です。
お金に関する情報を整理する
離婚を決めたら夫婦の年収や財産などを把握しておきましょう。
結婚後に夫婦で築いた財産を分け合うことになりますが、離婚を切り出した後では、相手の資産を確認することが困難になる場合があるからです。
夫婦の共有資産は、結婚後に夫婦で築いた財産です。
預貯金や不動産、有価証券、生命保険、さらには退職金まで幅広く対象となります。
「夫の方が支払ってきた金額が多い」ケースがあるかもしれません。
しかし、妻の協力があってこその財産となるため、夫婦の共有財産となるのです。
現実的な問題として、離婚を意識した相手が預金を移したり、資産を隠そうとするケースも少なくありません。
そのため、配偶者に気づかれる前に通帳のコピーを取ったり、不動産の登記簿謄本を取得しておくことが重要です。
証拠を残す
離婚の原因の多くは「性格の不一致」だと言われていますが、それだけでは離婚を認めてもらうのは難しいかもしれません。
夫婦関係が破綻していると証明できれば、主張が認められる可能性があります。
DVや浮気、モラルハラスメント、ギャンブルなどが原因で離婚を考える場合は、離婚を有利に進めるために証拠を残しておきましょう。
浮気の証拠収集は特に専門的な技術が必要です。
自力での調査では相手に気づかれてしまうリスクがあり、かえって証拠隠滅を招く可能性もあります。
確実な証拠を押さえるためには、プロの調査員による浮気調査が効果的です。
離婚届を勝手に提出されるのを防ぐ
通常、離婚届は夫婦間で合意の後、署名・押印し提出するものです。
しかし、合意が無かったとしても書面が整ってさえいれば受理されてしまいます。
離婚条件がまとまっていないのに勝手に離婚届を提出されるのを防ぐには、「離婚届不受理申出」を役所に出しておくことが有効です。
この手続きは本籍地または住所地の市区町村役場で受け付けており、一度受理されると有効期限はなく、本人が取り下げない限り効力が続きます。
そのため、離婚の合意が成立していない段階では、早めに申出を行っておくと安心です。
離婚したいと打ち明けてからすること

離婚したいと打ち明けた後は、お金や子どもについての話し合いを進めていきます。
感情をぶつけ合っても話が進まないため、冷静に話し合う必要があります。
話し合いの内容は、メモや録音などで記録しておきましょう。
口約束だけでは、後々トラブルに発展する可能性があるためです。
特に養育費や慰謝料などの金銭的な約束は、後から「言った、言わない」の争いになりがちです。
財産分与についての話し合い
財産分与とは、結婚後に夫婦で築いた財産を分け合うことです。
収入の無い専業主婦(夫)であっても請求できますので、しっかり取り決めをすることが大切です。
財産分与の対象となる「夫婦共有財産」は多岐にわたります。
現金や預貯金はもちろん、不動産、生命保険、学資保険、家財道具、退職金、年金、有価証券、貴金属なども含まれます。
一方で、マイナスの財産として住宅ローンや学資ローン、借金なども分与の対象となることを理解しておきましょう。
財産分与は原則として2分の1ずつの分割となりますが、特別な事情がある場合は割合が変わることもあります。
たとえば、一方が特別な技能で高収入を得ている場合や、相手方が浪費やギャンブルで財産を減らした場合などです。
- 現金、預貯金
- 不動産
- 生命保険、学資保険
- 家財道具
- 退職金、年金
- 有価証券
- 貴金属
親権と養育費の決定
子どもに関しては、親の都合ばかりを押し付けるのではなく、子どもが幸せになることを考えておくのが大切です。
離婚するにあたって、どちらが親権をもち、どのように養育費を負担していくかの話し合いが必要です。
親権者の決定は子どもの年齢、生活環境、経済力、監護実績などを総合的に判断されます。
子どもが幼い場合は、主たる監護者(主に子どもの世話をしていた親)が優先される傾向があります。
養育費については、裁判所が公表している算定表を参考に金額を決めることが一般的です。
お互いの年収と子どもの人数・年齢によって標準的な金額が算出されます。
ただし、子どもの特別な事情(習い事や塾費用、医療費など)については別途協議が必要になることもあります。
離婚協議書から公正証書へ
離婚協議書は、話し合いで合意した内容を記録した書類です。
財産分与や慰謝料、親権者、養育費、面会交流について具体的に記載していきます。
ただし、離婚協議書は法的な効力が弱いため、離婚協議書をもとにして、公正証書を作っておくと安心です。
公正証書の大きな利点は、養育費などの支払いが滞った場合に強制執行ができる点です。
ただし、この効果を得るには「強制執行認諾文言」の記載が必要で、この文言がなければ通常の契約書と同じように裁判を経て判決を得る必要があります。
作成は原則として夫婦双方が公証役場に出向いて行いますが、病気などやむを得ない事情がある場合は代理人による手続きや、別々の日に出向くことも可能です。
事前に公証人と条件を整理し、正式な作成手続きに進みます。
費用は養育費や慰謝料などの総額に応じて算出され、数千円から数万円程度が一般的な目安です。
話し合いがまとまらない場合は、離婚調停に進んでいきます。
24時間365日無料相談
離婚後の手続きと優先順位

離婚後に必要となる手続きは大変多く、優先順位をつけて進めていく必要があります。
名字や住所に変更の有り無し等、人によって内容が変わってくるため、変更内容をしっかりまとめておきましょう。
必要な手続きを把握できたら、それぞれの手続き場所や期限、必要書類を確認し、揃えていくと効率よく進めらます。
離婚届と同時にできる手続き
離婚しても旧姓に戻さない場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
提出期日が離婚から3ヵ月と短い期間になっているので、離婚届と同時に提出するのがいいでしょう。
この手続きを忘れてしまうと、一度旧姓に戻ってから再度家庭裁判所で氏の変更許可を得る必要があり、手間と時間がかかってしまいます。
戸籍と住民票の手続き
離婚後は、まず戸籍と住民票の変更を済ませることが重要です。
離婚届を提出する際に「結婚前の戸籍に戻る」か「新しい戸籍を作る」かを選び、本籍地や筆頭者を記載する必要があります。
自動的に処理されるわけではなく、離婚届での明示が必須です。
住所が変わる場合は、同一市区町村であれば転居届、異なる市区町村であれば転出届と転入届を提出します。
これらの手続きは、引っ越し前後14日以内に行う決まりになっています。
身分証明書の変更
戸籍と住民票の変更を終えたら、身分証明書の切り替えを行います。
これらはその後の各種手続きに必要となるため、早めに対応することが大切です。
マイナンバーカード
住所や氏名が変わった場合、14日以内に変更手続きを行う義務があります。
放置すると法的な不備となるため注意が必要です。
運転免許証
住所地の警察署や運転免許センターで手続きが可能です。
必要書類は住民票、新住所を確認できる書類、印鑑などです。
平日に行けない場合でも、一部の運転免許センターでは日曜日の受付に対応しています。
パスポート
平成26年以降、訂正制度は廃止されています。
現在は「残存有効期間同一旅券(6,000円)」または新規発行(10年用16,000円、5年用11,000円)のいずれかで手続きを行う仕組みになっています。
健康保険と年金の重要な変更手続き
離婚後は扶養から外れるため、14日以内に国民健康保険へ加入する必要があります。
会社員は「被扶養者異動届」を提出し、資格喪失証明書を受け取って手続きします。
年金も同様に、第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替えが必要です。
国民健康保険と国民年金には、減額や免除の制度があります。
年金には全額免除から4分の1免除、納付猶予や失業特例もあるため、経済的に厳しい場合は市区町村に相談してください。
年金分割の重要性
婚姻期間中の厚生年金は離婚後2年以内に分割請求できます。
「合意分割」と「3号分割」があり、特に専業主婦(夫)期間が長い場合は老後資金に大きな差が出ます。
手続きは年金事務所での情報提供請求から始まります。
子どもに関する手続き

子の氏変更と戸籍移動
両親が離婚しても子どもの戸籍と姓はそのままです。
変更する場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得て、市区町村役場に「入籍届」を提出します。
申立てには子ども一人につき収入印紙800円と郵便切手が必要です。
15歳以上は本人、15歳未満は親権者が申立てを行います。
ひとり親家庭への支援制度
離婚後は児童扶養手当を利用できます。
申請は市区町村役場で行い、認定まで2〜3か月かかります。
このほか、医療費助成や就学援助、住宅手当など自治体独自の支援もあるため、確認して申請しましょう。
学校や保育園での手続き
居住地が変わると、幼稚園・保育園・学校で住所や緊急連絡先の更新が必要です。
転校の場合は、在学証明書と教科書給与証明書を現学校から受け取り、新しい学校へ提出します。
公立は住民票移動に伴って手続きが進み、私立は個別調整となります。
また、離婚は子どもに大きな影響を与えるため、心理的ケアについても学校や保育園に相談しておくと安心です。
手続きでつまずいた時の対処法
.jpg?w=640&h=360)
専門家のサポートの重要性
離婚後の手続きは複雑で、一人ですべてを完璧に行うのは困難です。
財産分与や親権、養育費などの重要な事項については、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
また、離婚の原因が浮気やDVなどの場合、証拠収集の段階から専門家のサポートを受けることで、より有利な条件で離婚を進められるかもしれません。。
探偵事務所に相談するメリット
浮気の疑いがある場合、素人が調査を行うと相手に気づかれてしまい、証拠隠滅を招く危険性があります。
プロの探偵による調査であれば、法的に有効な証拠を安全に収集することがで可能です。
T.L探偵事務所では、調査だけでなく離婚後の生活再建についてもサポートを行っています。
離婚を検討している段階から、手続きの進め方、必要な準備、将来の生活設計まで、依頼者に寄り添ったアドバイスを提供しています。
特に女性相談員による対応も可能ですので、同性だからこそ話しやすい悩みや不安についても気軽に相談していただけます。
離婚は人生の重要な決断です。
一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けながら、より良い未来に向けて歩んでいきましょう。
こちらもチェック
24時間365日無料相談
まとめ
離婚手続きは想像以上に多岐にわたり、それぞれに期限や注意点があります。
事前の準備不足や手続きの順序を間違えると、後々大きなトラブルに発展する可能性もあります。
特に財産分与や子どもの親権、養育費などの重要事項については、感情に流されず冷静に判断することが重要です。
そのためにも、離婚を決意した段階から計画的に準備を進め、必要に応じて専門家のサポートを受けることをおすすめします。
離婚は終わりではなく、新しい人生の始まりです。
適切な手続きを経て、安心して新生活をスタートできるよう、この記事を参考に準備を進めてください。
T.L探偵事務所では、離婚に関する様々な悩みに対応しています。
証拠収集から離婚後の生活設計まで、依頼者の状況に応じたサポートを提供していますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。